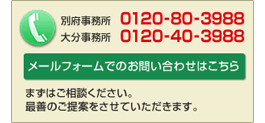ネットワーク
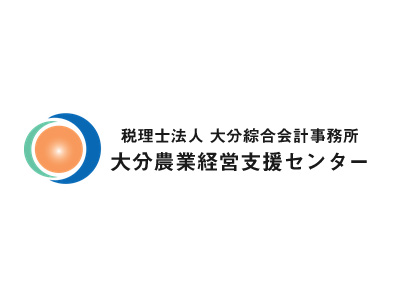
- ネットワーク
- ブログ
- 新着情報
- 未分類
2019年7月17日
農地バンク法案 可決
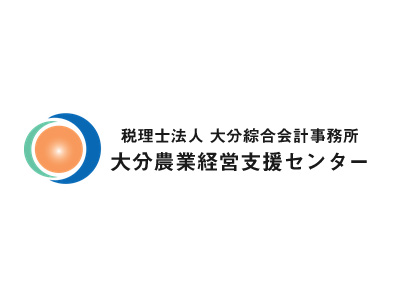
- 未分類
2018年12月10日
7年先の未来
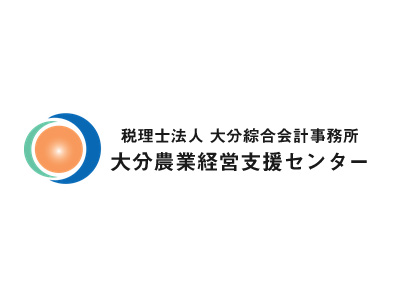
- 未分類
2018年10月15日
消費税の増税が、いよいよ現実のものとなってきました。
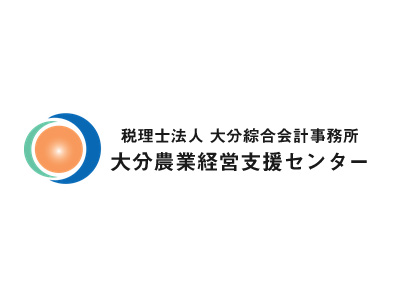
- ネットワーク
- ブログ
- 新着情報
- 未分類
2018年9月1日
農業経営基盤強化準備金制度の改正による注意点
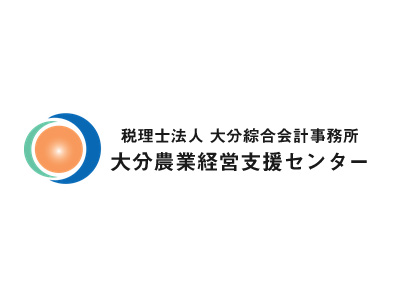
- 未分類
2018年5月31日
地域農業の未来
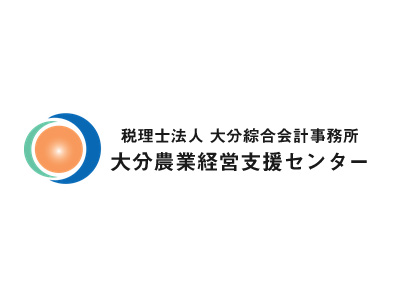
- 未分類
2018年5月1日
中小企業等経営強化税制の申請タイミングにご注意
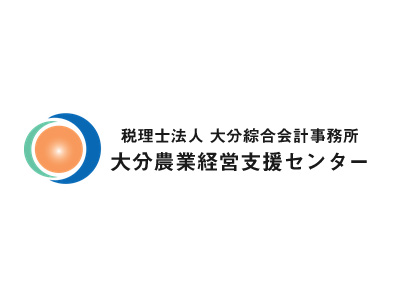
- ネットワーク
- ブログ
- 新着情報
- 未分類
2018年5月1日
消費税の税率改正に向けて
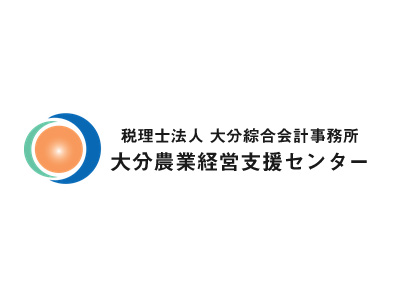
- 未分類
2016年12月29日
今年も一年ありがとうございました。
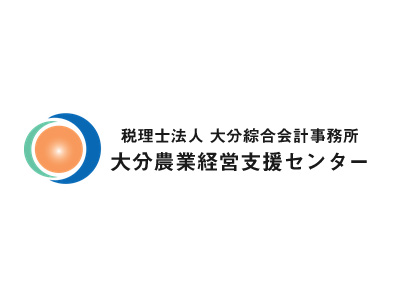
- 未分類
2016年6月1日
農地流通の新たな動き
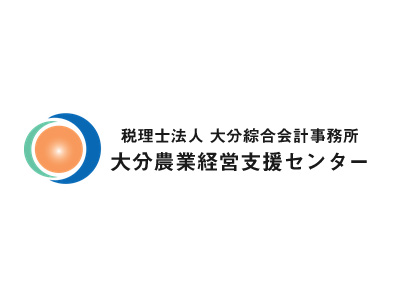
- ネットワーク
- ブログ
- 新着情報
- 未分類
2016年5月25日
食の安全をどこまで守れるか。