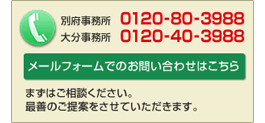お世話になります、大分事務所の荒木です。
今年度も残すところ1ヶ月となりました。季節は啓蟄ということで、草花や虫たちも動き出すころです。
私たちも日々の業務をやりながら来年度に向けた活動をしていくころかと思います。
3月決算を向かえる法人も多いと思います。そこで、今活性化しつつある税制の中に
所得拡大税制というものがあります。税制自体は目新しいものではないのですが、先般の改正で
かなり活用しやすくなっており、ぜひ検討される価値が多いと思いますのでご紹介します。
税制の内容としては、簡単に申し上げると(雇用者の)所得を拡大した企業の一定額の税額控除ができるというものです。
似ている税制に雇用拡大税制というものがありますのでご注意いただきたいのですが、
こちらは、事前届の上、計画的に人材を採用した場合に税額控除が受けられるものです。
話が戻りますが、所得拡大税制の大きなポイントは2つ。
①25年の(役員と役員の一定範囲の親族を除く)雇用者の給与に比べて同26年の給与が2%~5%(年度によって設定)増加していること。
②25年度以前から引き続き26年中に在籍した方の給与が増加していること。(25年中に退社した方や26年中に採用された方を除きます。)
その他、これらの条件を満たせば、給与の増加額の10%と法人税の10%(中小企業20%)と少ない方を税額控除できます。
弊社のFAX通信の所長記事にもありましたが、経営安定的に成長されている企業は比較的従業員への還元など待遇が充実していることが
そう思って、こんなタイトルにしました。
それ以外に、いくつか要件がありますので、詳しくは経済産業省 所得拡大税制 手引き