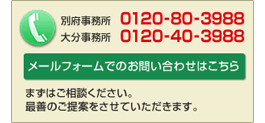お世話になります、大分事務所の荒木です。
今年一年色々な方にお会いし、勉強させていただき本当にありがとうございました。
まだまだ自身の知識不足を痛感させられ来年は一層頑張らないといけないと思います。
来年の干支は、「未」ということで、相場的には辛抱の年だとか。
一方で羊は群れをなすことからも家族安泰と平和な暮らしを意味するそうで、
間違っても戦争などない1年であることを切に願うと共に、食料的な災害が起こらないことを祈っております。
この一年農業分野での活動を最も感じたことは、経営規模の大小に関わらず、業績管理の分野に未着手の経営体が
多いということでした。
もちろん感覚的には優れたものをお持ちで、これまで継続発展されてきたということは
その感覚がすばらしいということではあると思いますが、現実的には微妙にズレが生じているというのが
正直なところではないでしょうか?
経営体として成長が早い所は、月次会計による業績管理が定着しているところが多いようです。
月次管理の最大のメリットは、タイムリーな修正と対策による改善・発展にあります。
1年に一回ででた業績は、もはや過去の栄光でしかなく、そこから得られる情報は現代の潮流からすると限定的なものになりかねません。また、月次管理をすることで経営計画がさらに活きてきます。
日々の業務の多忙さを理由に後回しにしていないでしょうか。
強い農業・経営を目指すのでれば避けては通れないことです。それなら早い方がいいでしょう。
ぜひ、まもなく2015年が始まります。一年の計は元旦にありますから、お悩みの方は
まずは、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。我々もご協力させていただきます!
それではよいお年を!