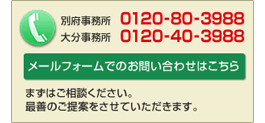お世話になります、大分事務所の荒木です。
平成28年10月19日の日経新聞記事からの紹介で
農林水産省が経団連などと組み、期間限定の取り組みではありますが、農業法人への民間人材の派遣を始めるようです。
農業企業に財務などの経営専門人材が不足していることを受けての取り組みようです。
原価どれくらいで、いくらぐらい儲かったというような経営的感覚を持たれている経営者は多いと思います。
しかし、売上がいくらで、原価がどれくらいかっかた。これはもう少し減らせる・減らさなければならない
どれくらい利益・収支が見込めるから、給与としていくら還元する、設備投資資金としていくら用意するというような戦略的な形での判断は少ないように思います。まして、今夏秋のように天候などの環境が不順で
予定したような収量がとれない場合あわてて資金調達をするというようなケースもあるかと思いますが
きちんと目に見える形で収益管理しておけば、第三者である金融機関への説明もしやすいかと思います。
あわせて隣の記事には、農業関連企業の再編後押しということで
農業体へ資材や材料を提供する関連企業の再編を後押しするため低利での融資を行うという記事もありました。これはまだ検討段階ですが、ご紹介です。